切迫早産や早産について、以前、次のような記事を書きました。

日本の早産の割合はおおよそ5%程度。
そしてそれよりも多くの方が「切迫早産」と診断されて治療しています。
その切迫早産の治療薬として最も有名なのが、子宮収縮抑制薬。
この子宮収縮抑制薬は、日本と海外で使用方法が大きく異なる薬剤でもあります。
母体へのリスク、赤ちゃんへのリスク、早産になるリスクなど、色々なものを天秤にかけながら治療していくわけですが、グレーゾーンも多い領域です。
今日は子宮収縮抑制薬の至適投与期間について、簡単に記事をまとめていこうと思います。
目次
1. 推奨投与期間は”48時間”

1. リトドリンと硫酸マグネシウム
妊娠16〜36週の切迫流早産妊婦に適応があるのがリトドリンです。
また、妊娠22週以降の切迫早産で、リトドリン単独では子宮収縮の抑制効果が得られない場合や、リトドリンが使えない症例に対して用いられるのが硫酸マグネシウムです。
どちらも子宮収縮抑制薬として国内で保険適用が認められており、日本でも広く用いられています。
2. 至適投与期間は?
日本産婦人科学会が出しているガイドラインでは、リトドリンの投与期間について次のような記載があります。
リトドリン塩酸塩の有用性については、
「コルチコステロイドの1クール投与」あるいは「未熟児管理の可能な施設への母体搬送」を目的とした場合に限り、
48時間以内の持続点滴投与法が支持されている。
実は、子宮収縮抑制薬の効果はおよそ48時間までしか認められていないのです1,2)。
| 子宮収縮抑制薬 | 48時間までの効果 | 7日までの効果 | 37週未満の早産 |
|---|---|---|---|
| リトドリン | あり | あり | 減らない |
| 硫酸マグネシウム | なし | ? | 減らない |
リトドリンを含めた子宮収縮抑制薬は、短期的な早産の予防効果はあっても、長期的な予防効果はありません。
あくまでも母体搬送や、ステロイド投与のための時間稼ぎとして用いられる薬であるというわけです。
ただ、これをみた多くの妊婦さんは、びっくりされることと思います。
え…でも私は、入院して何週間も張り止めの点滴を続けています…。
そうなんですよね。
日本の現場では、子宮収縮抑制薬の長期投与が当たり前のように行われています。
2. 日本では長期投与が日常茶飯事

1. 未熟性の予防のために
前述の通り、一般的には48時間を超える子宮収縮抑制薬の使用は推奨されていません。
その理由は、48時間を超える子宮収縮抑制を行っても早産率やNICU入院率、新生児予後の改善が見込めないからです1)。
さらに、薬剤による多くの副作用が生じる可能性があるからです。
アメリカでは妊婦さんの肺水腫や母体死亡の報告が相次ぎ、その副作用の頻度の高さが問題となりました。
ではなぜ日本では長期間の使用が行われているのか。
それには、日本における副作用の発現頻度が12.4%と、海外の報告よりも少ないことも影響しているでしょう。
そのため、未熟性による児の罹病率を極力少なくしようと、そちら側のメリットも考慮して使用しているわけです。

妊娠週数が少ないほど、赤ちゃんの脳障害・呼吸障害・壊死性腸炎などの合併症が多くなります。
母体と新生児のメリット・デメリットを天秤にかければ、妊娠34週まで妊娠期間を延長させることが切迫早産の管理目標の1つになります3)。
2. 長期間投与した時の妊娠延長効果は?
日本の研究では、48時間以上の長期間にわたって子宮収縮抑制薬を使用した症例について、次のような検討結果が出ています。
妊娠35週で子宮収縮抑制薬を中止
→35〜37週早産となった症例は22%、正期産に至ったのは29%
妊娠36週で子宮収縮抑制薬を中止
→48時間以内に分娩に至った症例は約30%
特に「軽度の子宮内膜炎」「やせ妊婦」「子宮頚管縫縮術」の症例で子宮収縮抑制薬の効果が高かった。
簡単にまとめれば、妊娠35〜36週まで子宮収縮抑制薬を長期に使用していた場合においては、薬剤が有効だったと考えられる症例は対象の2〜3割程度みられたということです。
海外では「有効性が乏しい」というエビデンスになっているとはいえ、臨床的な面で言えば効果がある妊婦がいることは事実です(多数派ではありませんが)。
長期間使用する際には、その有効性と母体の健康状態とをよく見極めて、投与期間を検討する必要があります。
3. 子宮収縮抑制薬の胎児・新生児への影響

リトドリンと硫酸マグネシウムはどちらも胎盤通過性があり、胎児や新生児にも影響をもたらします。
<リトドリンによる児への影響>
- 頻脈性不整脈(心房粗動・上室性頻脈)
- 心筋肥厚
- 心筋虚血
- 心不全
- 低血糖
- 高カリウム血症
- 乏尿 など
<硫酸マグネシウムによる児への影響>
- 骨形成異常
- 筋緊張低下
- 呼吸障害
- 高カリウム血症
- 低カルシウム血症
- 脳出血
- 動脈管開存症
- 低血圧 など
リトドリンは主に赤ちゃんの不整脈や心不全が問題となります。
また、5歳の時点における気管支喘息の罹患との有意な関連も報告されています。
一方、硫酸マグネシウムは、電解質異常や呼吸障害・筋緊張低下などに影響します。また、未熟児動脈開存症は呼吸不全・腎不全・壊死性腸炎のリスクとなります。
いずれも、投与期間・投与量の増加により副作用の発生が高まる傾向にあるため、使用は必要最小限にとどめることが重要です。
4. 実際の臨床現場では

私は今まで、大学病院・地方の周産期医療センター・都心の周産期医療センターなど、複数の施設で勤務してきました。
その経験から言うと、子宮収縮抑制薬をいつまで使用するかは「その施設による」としか言えません。
1. ある大学病院の場合
例えば大学病院では、基本的には48時間以内の使用に留めていました。
大学病院は夜間休日も複数の産婦人科医・小児科医・麻酔科医が当直をしていましたし、小児外科医も居ましたし、妊娠22週から対応できる医療資源が整っていたからです。
子宮収縮抑制薬を投与していることによってマスクされる可能性がある「感染」「切迫子宮破裂」などの症例を考慮しても、長期投与は避けるべきだという傾向にありました。
早産期に子宮収縮抑制薬を切った場合、実際に早産になる人が半分、正期産までもつ人が半分、といったイメージです。
陣痛・破水がいつ起きても対応出来るという安心感があるが故の短期投与だなと思っています。
2. ある周産期医療センターの場合①
妊娠25週以降から対応している施設でした。
この施設では、小児科の先生との協議のもと、妊娠34週頃までは子宮収縮抑制薬を継続、以降は中止、という方針でした(もちろん症例に応じて前後しますが)。
妊娠34週に入ったあたりで薬剤を中止するわけですが、やはり長期に投与している人ほど張り返しが強く、早産に至る例が多かったです。
3. ある周産期医療センターの場合②
妊娠34週以降から対応している施設でした。
この施設では、基本的には妊娠36週まで子宮収縮抑制薬を継続する傾向にありました。妊娠34週以降から開始することもありました。
個人的には少し過剰だなと感じていましたが、夜間などの緊急時の対応が手薄であったり、出来る限り緊急で何かが起きることを避けたいが故の社会的理由もあるように思います。
5. 結語

子宮収縮抑制薬をいつまで使用するかは、施設・担当医によって結構幅があります。
ガイドライン上は
「基本的には48時間以内の使用に留め、それ以上継続する場合は減量・中止の可否も検討した上で選択するべき」
と記載されていますが、例えば早い週数に対応出来る病院の数が少なかったり、早産に伴うリスクを考慮して出来る限り週数を延ばしたいという意識が働いたりと、様々な思考が巡るわけです。
実際、子宮収縮抑制薬は、患者さんが自覚するお腹の張りを軽減させます。
見かけ上の子宮収縮の頻度が減ることによって、臨床的にも効いているように思えることも多いです。
ただ、それが妊婦さんにとって本当に必要なものなのかをしっかり判断することが大切。
私たち産婦人科医も、週数だけにこだわらず、赤ちゃんや母体の合併症にももっと意識を向けながら治療方針を考えていかなければなと思う次第です。
いかがだったでしょうか。難しい話題なので、ちょっと曖昧な表現もあったかと思いますが、それだけグレーなんだなと思っていただければ幸いです。
日本の早産率は5%なのですが、世界の推計早産率は9〜11%程度と2倍だったりするので、長期投与の良い面もあるのかもしれない、とは思ったりもします。
日本が今後どんどん短期投与に切り替えるようになったらどうなるのか、今後の研究も待たれます。
最後に、少しでも多くの方にこのブログをご覧いただけるよう、応援クリックよろしくお願いします!








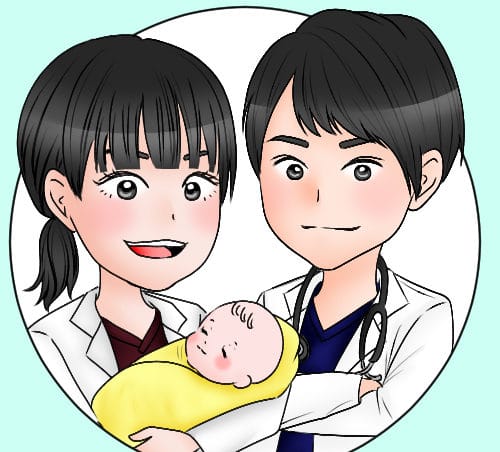





















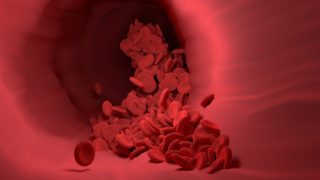








こんにちは、ゆきです。産婦人科医として働いています。